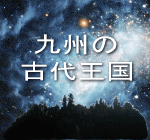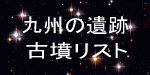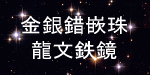金銀錯嵌珠龍文鉄鏡,金銀錯嵌珠龍紋鉄鏡,卑弥呼の鏡,蕨手文,
わらびてもん,日田,鉄鏡,九州,筑後川,装飾古墳,
装飾,古墳,壁画,彩色,円文,同心円文,
古代,卑弥呼,シャーマン,女王,邪馬台国,呪術,
鬼道,横穴式石室,福岡県,うきは市,女王の鏡の修理人,
| 金銀錯嵌珠龍文鉄鏡 TOP | 金銀宝飾品が出土した遺跡・古墳 |
ダンワラ古墳
| ダンワラ古墳 石室の配置図 |
| ダンワラ古墳 大分県日田市日高町 古墳の上部表面は1933年当時、畑として使われており、高さ約4m、広さ9アール(900平方メートル) 直径30mの円墳がちょうどおさまる大きさです。 高さ4mの盛り土のかなり下の方、火山灰の地面近くに古式古墳の長方形の竪穴があり、その中の西側で金銀錯嵌珠龍文鉄鏡が発見されました。この竪穴は長さが4〜5mある長い方形で、鏡から東北に当たる位置には、鉄刀や轡などの馬具も間隔を置いて納められていました。またこの竪穴とほぼ同形の竪穴が、東に約8m離れたところにも平行して存在し、その竪穴内東側からは碧玉の管玉、水晶の切子玉、玻璃(ガラス)の小玉類も出土しています。 以上は1962年当時京都大学教授であった梅原末治氏の金銀錯嵌珠龍文鉄鏡についての論文の一部を、わかりやすく書き直したものです。 金銀錯嵌珠龍文鉄鏡を発見した渡辺音吉氏によると、鉄鏡と一緒に出土した馬具は鐙(あぶみ)と馬の口につける金具であったということです。また横穴から1mほど掘り下げた横穴に近いところからは大量の壺や甕などの須恵器が出土し、さらに近くからは勾玉やガラス玉なども見つかったそうです。 なおこのダンワラ古墳発見のきっかけは近くの鉄道工事用の盛り土採取による破壊であったため、現在はその痕跡はありません。ダンワラ古墳はアカホヤと呼ばれる、水はけの良い火山灰の上に作られていました。 2.5ミリという、ごく薄い鉄の鏡が千数百年の時を超えて奇跡的に形を残すことができたのは、この特殊なガラス質の火山灰のおかげのようです。 金銀錯嵌珠龍文鉄鏡は1世紀〜3世紀に作られたものですが、鉄鏡が納められていたダンワラ古墳の竪穴式石室は、出土した辻金物の細工から、5世紀〜6世紀に作られたものだということです。(梅原末治氏の論文より)よって鉄鏡の持ち主の死後は末裔に受け継がれ、5世紀以降に当時の末裔と共に葬られたと推測されます。 |
*
| ダンワラ古墳 石室の配置図 --- 梅原末治氏の論文と鏡発見者である渡辺音吉氏の説明より |
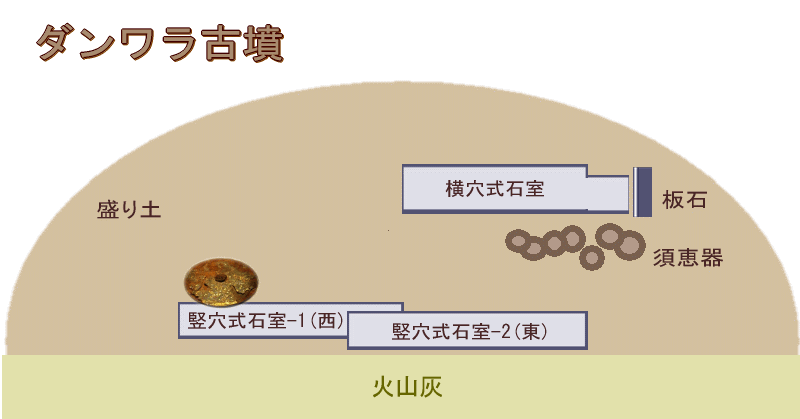 |

|